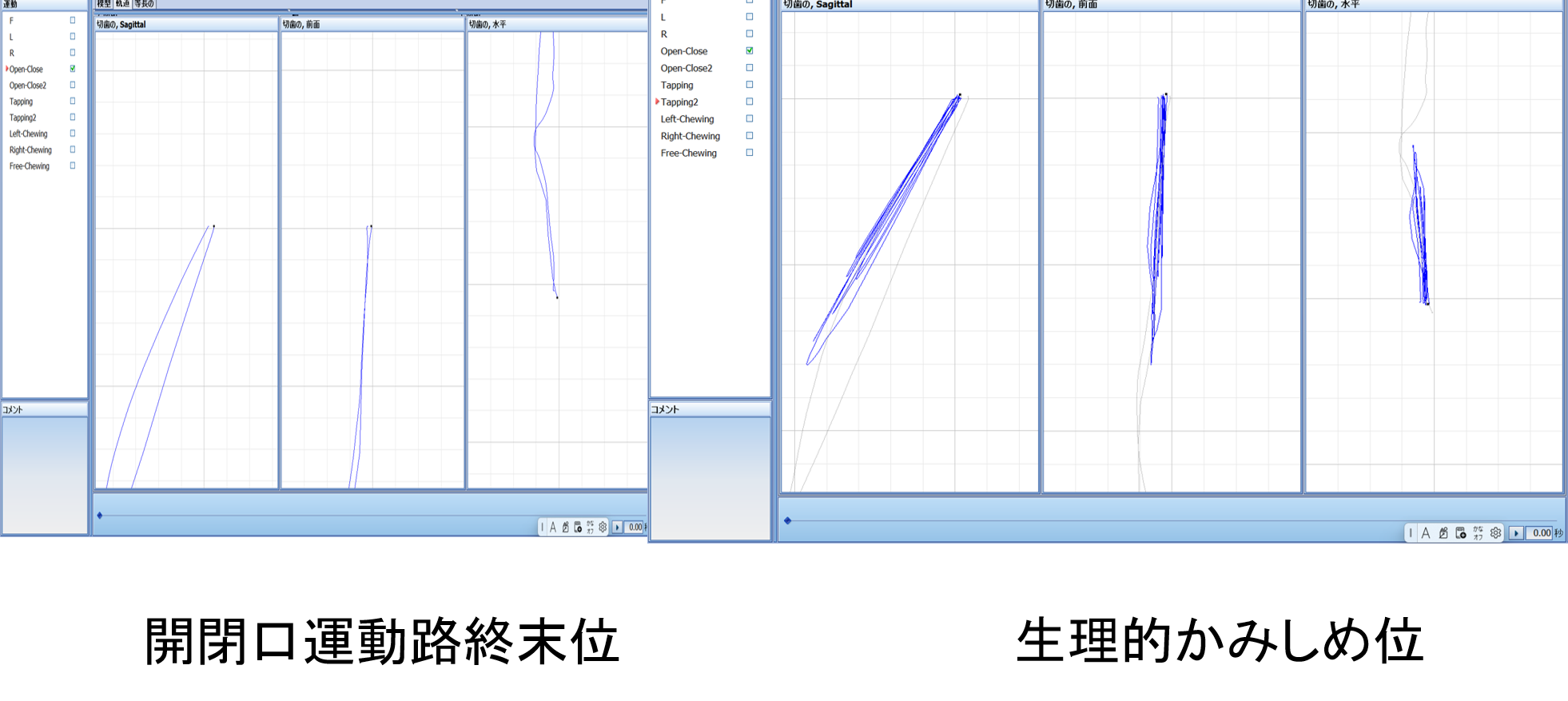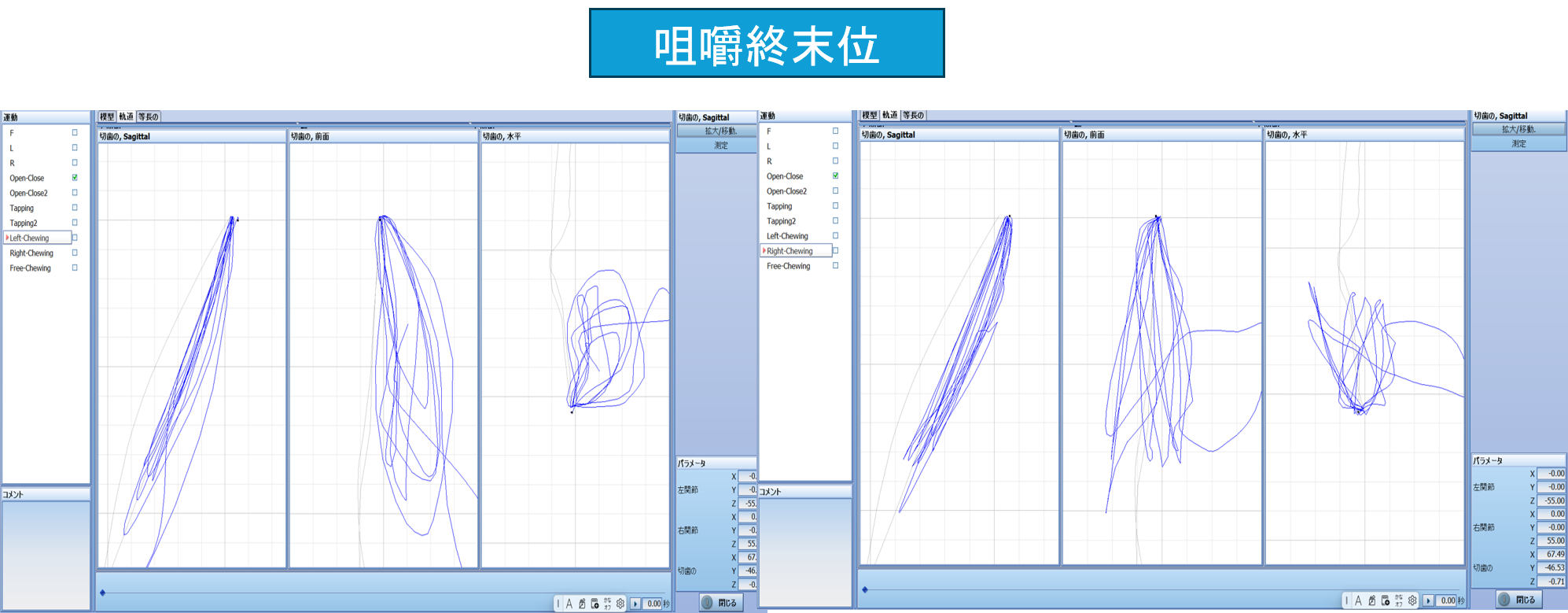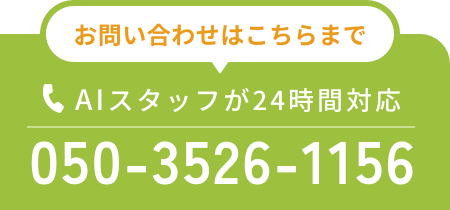当院で行っている咬合検査
シリコーンブラック検査法(咬合接触検査)

①検査目的
明確でない咬合接触像の把握のため
②検査で分かること
咬合力を発現させない状態における咬合接触像、咬合接触面積
咬合支持域、支持咬頭の観察
複数回検査することにより咬頭嵌合位のずれがわかる
③検査で分からないこと
その咬合接触像の良否
咬合採得の是非
実際に口腔内で取ったブルーシリコンになります。 抜けているところが咬合接触点、当たっているところが咬合近接域になります。

複数回とり、咬頭嵌合位の再現性を評価していきます。
また、Drの指示で患者さんに軽度、中度、強度 咬む圧を指示をして採得することもあります。
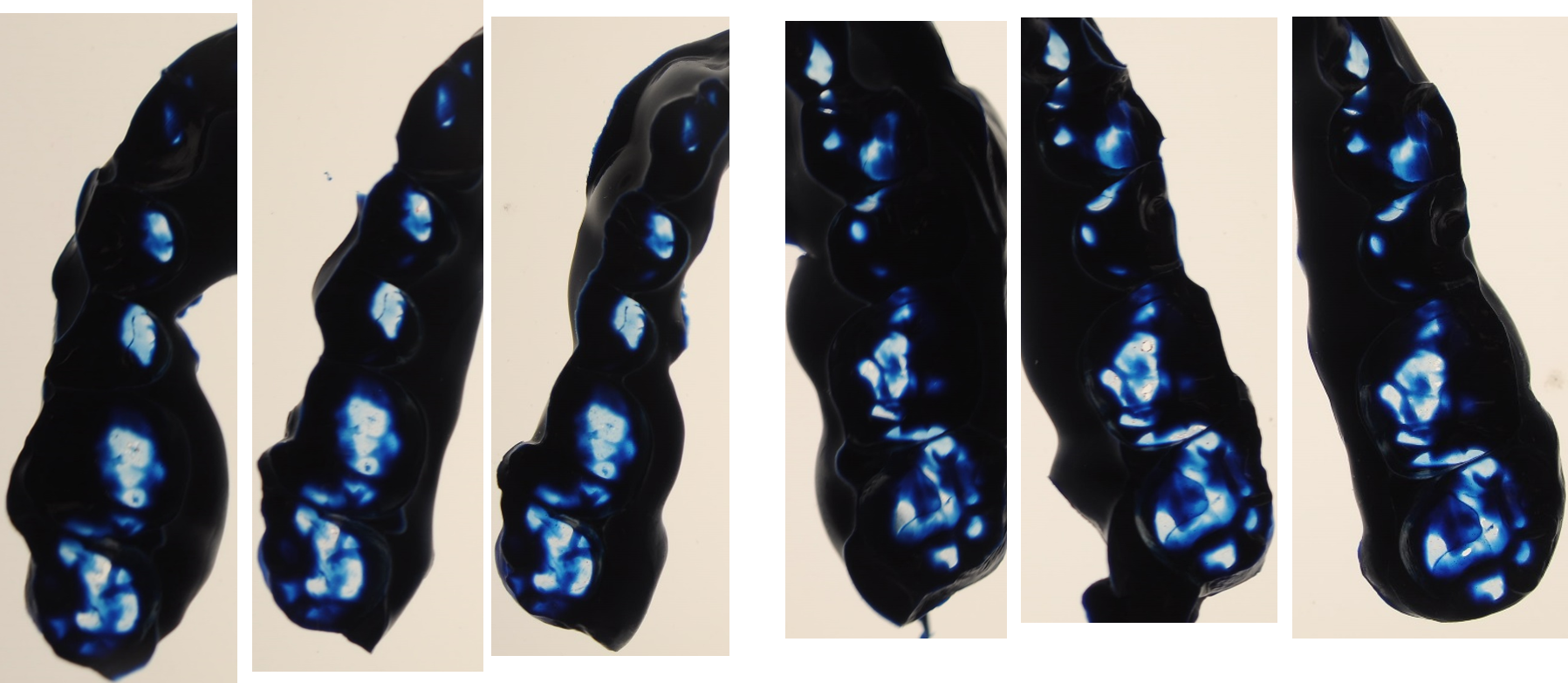
引き抜き試験検査法 レジストレーションストリップス
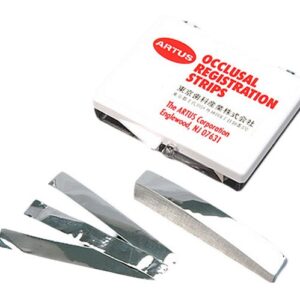
①検査目的
咬合接触強さの可視化
②検査で分かること
厚さ 8㎛ 咬合接触点(トゥルーコンタクト)
厚さ12.5㎛ 咬合近接域(ニアコンタクト)の把握
③検査で分からないこと
咬合接触面積
その咬合接触像の良否
咬合採得の是非
模型咬合検査法

①検査目的
・舌側面観からの咬合接触の可視化
・フェイスボゥトランスファによる仮想咬合平面の可視化
②検査で分かること
患者の口腔内がなくても立体的にほぼ等倍で観察できる
歯の歯冠形態(咬耗、破折、楔状欠損など)
欠損部位、その状態
歯列状態(上下歯列)
③検査で分からないこと
歯周組織の状態
模型は台座をつけて、上下顎の咬合面、側方に加えて舌側面観からの咬合接触を確認します。
舌側から見ると小臼歯が当たっていない、無接触のことが多かったりもします。
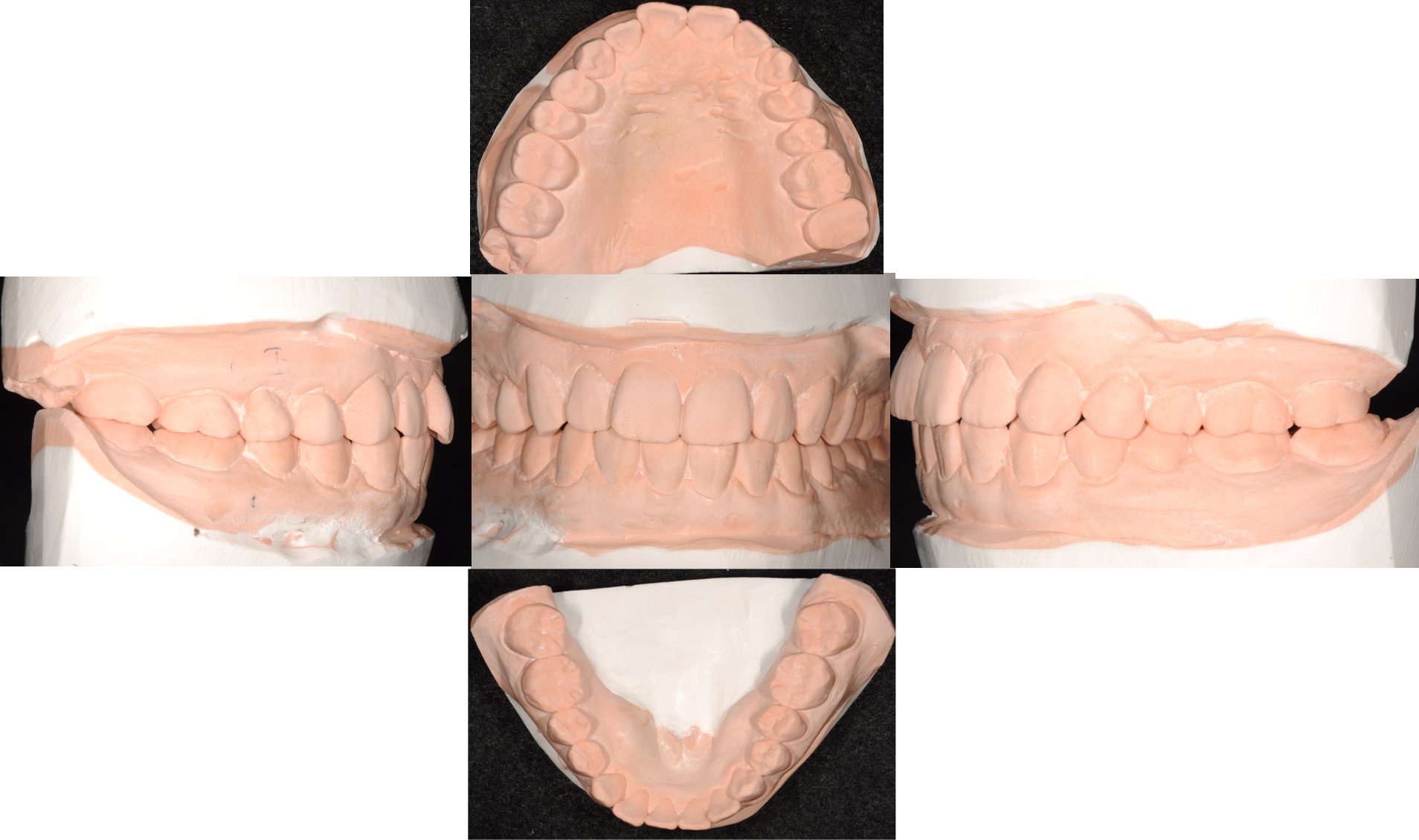
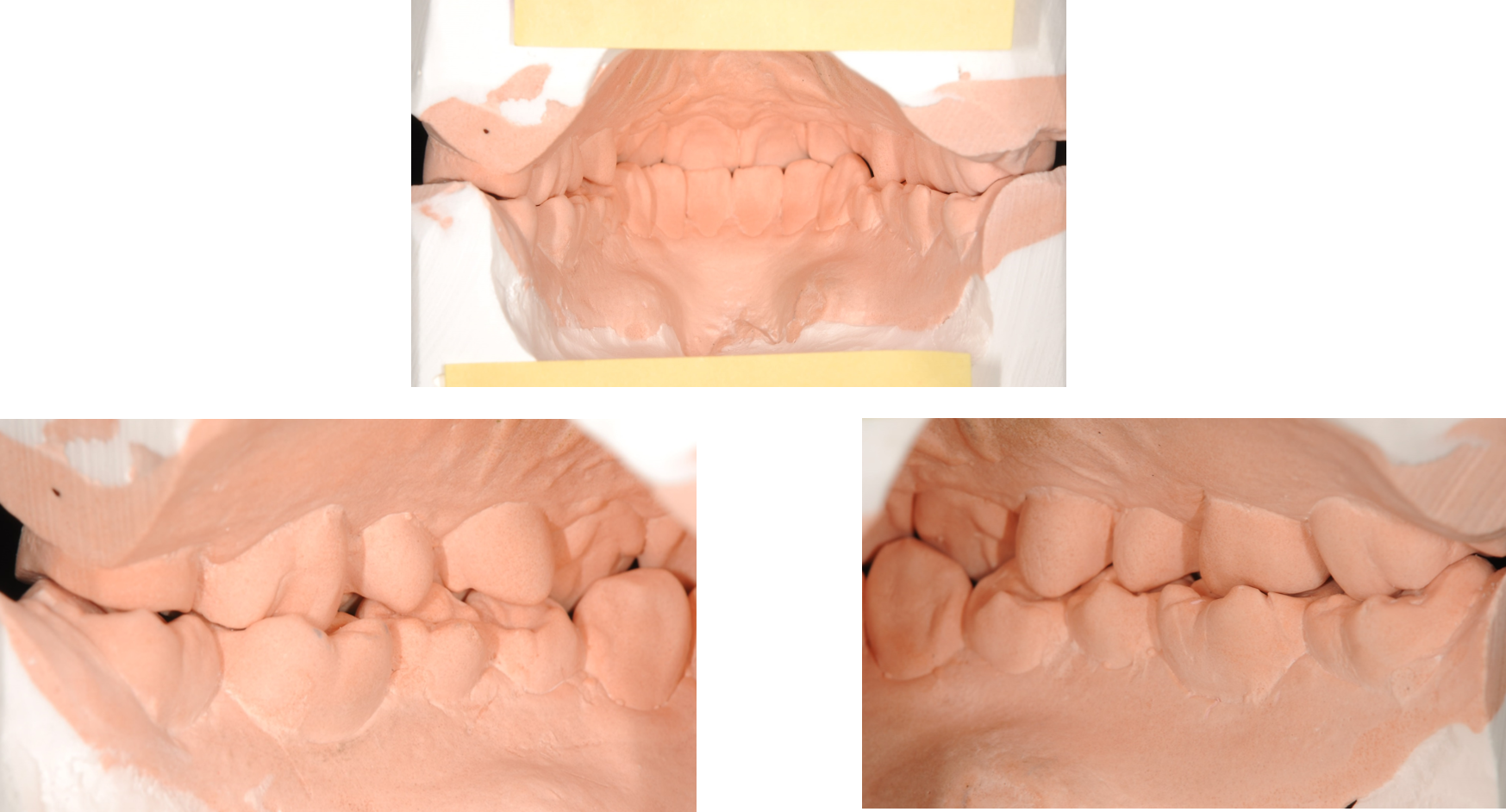
下顎運動検査法 (アルクスディグマⅡ)

①検査目的
・咀嚼運動終末位、習慣性開閉口運道路終末位の可視化
・咬頭嵌合位の咬合採得
・CBTを使っての可視化
②検査で分かること
咬頭嵌合位のずれ
早期接触
③検査で分からないこと
動的な咬合干渉(咬頭干渉)部位
検査項目とその目的
アルクスディグマⅡでの検査項目としては以下の項目があります。
左手の写真はフロント 下あごを前に出した時の動きです
右手の写真はオープンクローズ 習慣性開閉口運動路終末位を見ています。
・Front,Right,Left~形態的な安定
・Open/Clouse~習慣性開閉口運動路終末位
・Tappinng~生理的かみ締め位
・Right,Left,Free Chewing ~咀嚼終末位
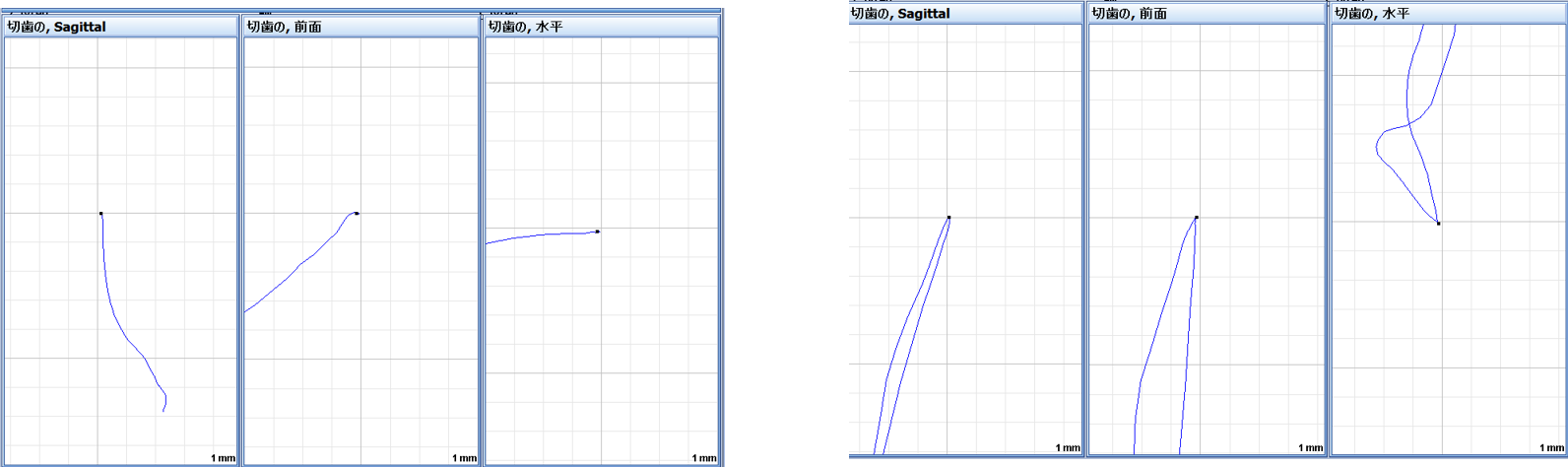
咬合接触圧検査法 デンタルプレスケールⅡ
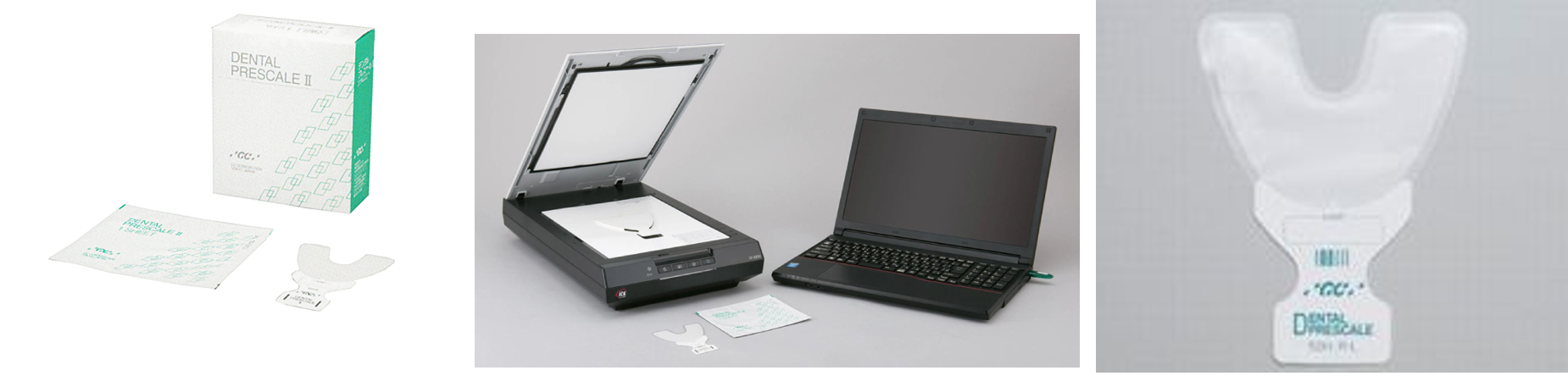
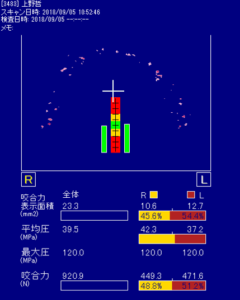
①検査目的
・「咬合接触点」の最大咬合力の可視化
・「咬合接触点」の咬合力表示面積の可視化
②検査で分かること
咬合圧分布の評価
最大咬合力・接触面積 左右的なバランスデータ
咬合接触点の数
③検査で分からないこと
その接触部位が正常か、病的か
M.M.R(下顎運動測定)⇒咬頭嵌合位の確認